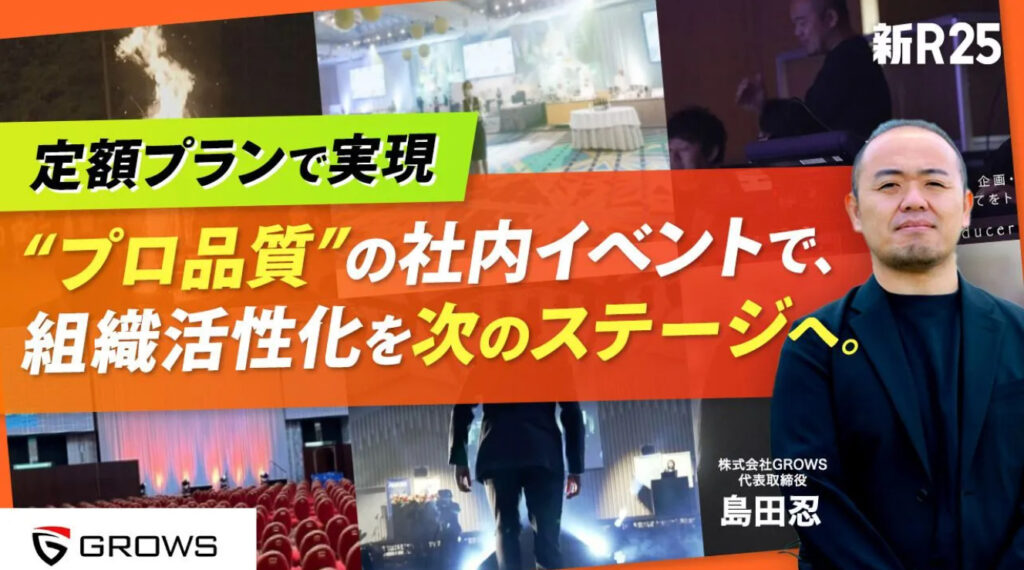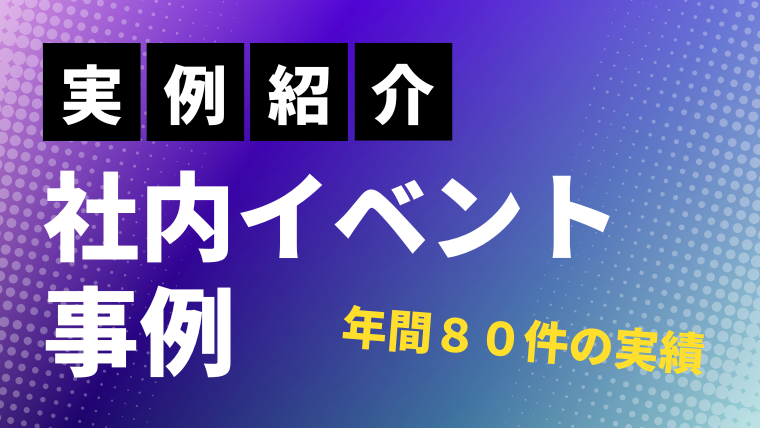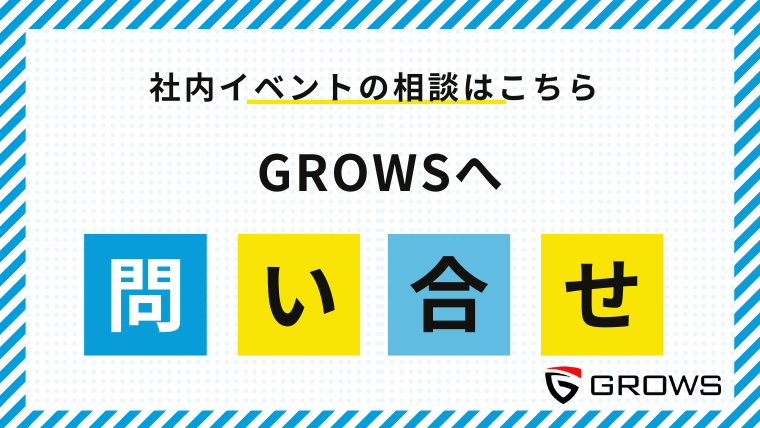「社員を讃える素敵なイベントにしたい」と思って準備を始めたのに、いざ企画を進めると悩みやトラブルが続出…。
社内表彰式は、ただの一つのイベントではありません。感謝や評価が全社員の皆さんに、見える形で届けられるからこそ、
「公平性」や「演出」や「空気感」など、気をつけるポイントが実は山ほどあるんです。
今回は、イベント制作の現場でよく聞く“困ったあるある”を10個厳選し、プロ目線の解決ヒントも添えてご紹介します!

社内表彰式の設計は想像以上に決めることや考えることがたくさんありますよね!今回は担当者さんが困ること10選を解説します!
① 誰を表彰すべきか決まらない問題
最初のつまずきポイントが、まさにここかもしれません。
「今年は誰を表彰する?」と役員に聞いても明確な回答が返ってこず、結局、去年と同じようなメンバーに…というケースは少なくありません。
また、評価基準が曖昧なまま進めると、「なぜあの人が?」「なぜうちの部署は一人もいない?」という不満や不信感が社内に広がることもありますので要注意です!授賞理由を明確に決めていくことは表彰式を成功させる一番のポイントになります。
表彰の目的を明文化することが第一歩です。
「業績貢献」「挑戦した姿勢」「バリュー体現」など、どんな行動を評価するのかを言語化し、選考基準を関係部署とすり合わせておきましょう。また、推薦制や部署ごとの推薦枠を設けると、納得感が生まれやすくなります。ぜひ参考にしてみてください!
② 表彰理由やコメントが薄い/間延びする
いざ表彰者が決まっても、次に悩むのが「どんな言葉を添えるか」です。
よくあるのが「○○さんは日頃から真面目に取り組んでおり…」といったテンプレ文が続き、全く印象に残らないパターンもあります。
逆に、何を言えばいいか分からず、当日その場で社長がアドリブでコメントして場が微妙な空気に…なんて事例もあります。
受賞者が「自分の仕事がちゃんと見られていた」と感じられるよう、具体的なエピソードを入れるようにしましょう。
同僚や上司に簡単なヒアリングをするだけでも、リアルなエピソードが手に入れることができます。
例えば「誰もが敬遠する難案件に手を挙げてくれた」など、一言加えるだけで温度が変わります。表彰状などをより具体的な内容にすることで授賞理由が明確になり、参加者に正確に理由を届けることができます。
③ 受賞者に事前連絡すべき?サプライズ?問題
社内表彰式では、サプライズで発表したいという意見もよく出ます。
たしかに驚きと喜びが入り混じる演出は印象に残りますが、うまくいかなければ逆効果にもなりかねません。
特に内向的な人が突然舞台に呼ばれ、マイクを渡されると、戸惑いや緊張が伝わってしまい、感動の瞬間が台無しになてしまいます。サプライズが良いのか?事前告知が良いのか?は社内での議論を行うようにしましょう。
「プレゼンテーションあり」なら、基本的には事前に受賞を伝える方が安全です。
ただし演出上どうしてもサプライズにしたい場合は、話さなくて済むように動画で紹介したり、コメントを事前に収録しておくなど、本人が焦らない工夫をしましょう。基本的にアドリブでできる人は少ないです。表彰の目的を明確にし段取りを組みましょう。
④ 表彰式の進行が盛り上がらない
どれだけ良い内容の賞でも、淡々と読み上げて、ただ拍手して…が繰り返されると、場の空気はあっという間に冷えてしまいます。
特に受賞者の人数が多い場合、会場の一体感が持続しないこともあります。単調流れを断ち切る仕掛けは表彰式の中に組み込みましょう。具体策としては映像を組み合わせたり、表彰の仕方に工夫をしたりします。表彰に変化をつけることで盛り上がりのポイントを演出上作っていくことが大切です。
プロのチェックポイント
進行に緩急をつけるために、「映像」「音響」「照明」「演出」の要素を組み合わせましょう。
受賞者紹介ムービーや、授賞タイトルのアタック演出も効果的です。
また、司会のトーク力も鍵となるため、社内に適任がいない場合はプロ司会者の起用も検討しましょう!
⑤ 登壇や立ち位置の動線でモタつく
表彰式で意外と見落とされがちなのが「人の動き」です。
受賞者がどこから登場して、誰から何を受け取り、どこに戻るのか。これが曖昧だと、流れが止まり、会場の緊張感も切れてしまいます。段取りを進行台本上で設計しておくことを意識し、段取りを決めておきましょう。
台本には、登壇者の動線(入口・立ち位置・退出方向)を詳細に書き込んでください。
登壇タイミングでBGMが切り替わるなど、動きに合わせた演出もあるとテンポが生まれます。
また、当日リハーサルは必須となり、リハで立ち位置をテープでマークしておくとよりスムーズな運営が可能です。
⑥ 社長スピーチが長すぎて空気が冷える
主催者として、社長が熱い思いを語ってくれるのはありがたいこと。
しかし、10分、15分と話が続くと、現場の空気はだんだんと硬直…。
冒頭で時間を取りすぎてしまうと、その後のプログラムにしわ寄せが来てしまうこともあります。
事前に「15分以内を目安に」などの目安時間を伝えておくことが大切です。
台本にメッセージの要点を添えて渡すと、構成を組み立てやすくなります。
どうしても長くなりそうなら、社長挨拶はオープニングではなく中盤に入れるというテクニックもあります。中盤に配置することで、プレゼンテーションを眺めに聞くことができるという心理的効果もあります。
⑦ 受賞できなかった人のモチベーションが下がってしまう
「またあの人か…」「うちの部署は一度も選ばれたことがない!」
表彰された人がいる一方で、されなかった人に無言の「温度差」が生まれてしまうのは避けたいところです。
特に年功序列や特定部門だけに偏ると、不公平感が高まりやすくなります。受賞者の選定と連動しますがバランスよく考えましょう。
「今年は○○部門の功績に注目」など、選定に一貫性があることを伝えましょう。
また、ノミネート者の紹介や、拍手タイムを設けると“見られている”感が広がります。
最後に「来年はぜひ皆さんの中からも!」という締めの一言も忘れずに入れるようにし、参加している皆さんへのメッセージングは忘れないようにしましょう。
⑧ 副賞選び
表彰式では、トロフィーや賞状以外に副賞を用意するケースが多いですが、「何を選べばいいか分からない」と悩む担当者も多いです。
高額すぎても会社の公平性が疑われるし、安すぎると失礼な印象になってしまいます。副賞はもらってうれしいものも大切ですし、記念に残ることも大切です。
物品+金券のハイブリッドがおすすめです。
例えば「社名入り高級ボールペン+Amazonギフト1万円」など。記念性と実用性が両立できます。
また、選べるギフトタイプ(カタログやWebポイント)も、好みが分かれる場では有効です。授賞のパネルなども用意することでより副賞が際立ちます。
⑨ 写真撮影や記録映像がグダグダ
「せっかくの表彰シーンなのに写真がボケてた」「全員の顔が写ってない」など、
イベントの記録は「証拠」であり、「社外発信素材」でもあります。撮れていなかったら二度と戻れません。しっかり撮影をし記録を残すようにしましょう!
プロのカメラマンに依頼するのがベストですが、難しい場合は“写真係”をしっかり任命し、当日の撮影リスト(誰を、いつ、どこで)を作成しておきましょう。
特に表彰の瞬間は、被写体の立ち位置・ライティング・目線が鍵になります。事前のシミュレーションを忘れずにしましょう。
⑩ 終わったあとに「来年どうする?」と誰も手を挙げない
イベントが終わってホッとしたのも束の間。
次年度の準備で「あのときどうしてたっけ?」「去年の資料どこ?」と混乱することはよくあります。
特に担当者が変わる場合、運営のノウハウがゼロからやり直しになってしまうのは避けたいところです。
式の後に必ず「運営ふりかえり会」を行い、実施後のフィードバックをまとめましょう。
成功事例も失敗例も残すことで、来年の担当者が“ゼロから考えずに済む”仕組みを整えることができます。
Googleドライブなどの共有フォルダにまとめておくのも効果的です。
【まとめ】成功のカギは“設計力と演出力”のバランス
社内表彰式は、感謝と承認が交差する、企業文化を象徴する時間です。
だからこそ、内容も空気も丁寧に設計し、「ちゃんと見ているよ」「価値を認めているよ」というメッセージが伝わることが大切です。
どんな表彰式にしたいのか。誰に、どんな想いを届けたいのか。
そのビジョンさえ明確であれば、準備のプロセスや演出の方向性も自然と見えてきます。
「ただやるだけ」ではなく、「伝わる形に」していきたい。
その一歩を踏み出すために、この10の「困った」とその対策が、少しでもお役に立てれば幸いです。